| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科学的試験名 | Scientific Title/ Scientific Title:Acronym |
必須 | ○ | テキスト | 1000 |
定義:正式な試験の題名
ノート:通常は、介入の名称、対象疾患、アウトカム、試験デザインに関する記述などが含まれます。
すでに倫理審査で承認を得ていたり、その他対外的な申請に用いた試験名がある場合、 その試験名を正式なものとして、この欄に入力してください。 (必ずしも、上記の記述が含まれていなくても構いません。) 例:疾患ABCに対する○○療法と××療法の有効性と安全性に関するオープンラベル多施設
共同ランダム化並行群間比較試験
略称 定義:「科学的試験名」の略号。例:ABC試験
|
| 科学的試験名/ 科学的試験名略称 |
必須 | ○ | テキスト | 1000 | ||
| Public title/ Acronym |
必須 | ○ | テキスト | 255 |
定義:一般の方にとっても容易に理解できるような表現とした、試験の題名
ノート:専門用語はなるべく使わず、一般の方にも理解が容易な表現としてください。
略称 定義:「一般向け試験名」の略号。例:ABC試験
|
|
| 一般向け試験名/ 一般向け試験名略称 |
必須 | ○ | テキスト | 255 | ||
| 試験実施地域 | Region/ 試験実施地域 |
必須 | ○ | チェックボックス | - |
定義:試験実施の地域(国際的地域)
選択肢:日本、アジア(日本以外)、北米、南米、欧州、オセアニア
ノート:複数選択可能です。 実施地域により、試験登録のための言語が異なり、入力画面も異なります。入力
画面の制御のために必要です。
日本が実施地域に含まれる場合:日本語と英語での登録が必要です。 (日本語と英語の入力欄が並んだ画面を用います。) 日本が実施地域に含まれない場合:英語で登録します。 (日本語の入力欄がなく、英語の入力欄のみからなる画面を用います。) |
| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象疾患 | Condition | 必須 | ○ | テキスト | 1000 |
定義:研究の対象とする疾患名、病態や状態
ノート:臨床薬理試験などで 健康な人に参加してもらう試験の場合、最終的にどのような 疾患を持つ人や状態の人に適用を期待しているか(Target population)に基づいて記載してください。
当該の試験で組み入れる、参加者の状態を記載するものではないことに注意してください。
この場合、『選択基準』に「健康な○○」を含めて記載してください。
健康な人が観察研究や予防的介入、スクリーニング介入などに参加する場合は、当該研究で予防したい健康状態や問題について記入する。 |
| 対象疾患名 | 必須 | ○ | テキスト | 1000 | ||
| Classification by specialty/疾患区分1 | 必須 | ○ | チェックボックス | - |
定義:対象疾患の診療領域
選択肢例:循環器内科学、呼吸器外科学、小児科学 など
ノート:対象疾患の分類に診療領域を利用します。試験を行う予定の診療科を基に
選択するとよいでしょう。複数選択可能です。
健康食品を評価する臨床試験で選択に迷う場合、「該当せず」を選んでください。 |
|
| Classification by malignancy/疾患区分2 | 必須 | ○ | 選択 | - |
定義:対象疾患が悪性腫瘍であるか、またはがん悪性腫瘍外の疾患か
選択肢:悪性腫瘍、悪性腫瘍以外
ノート:主に、悪性腫瘍を対象とした試験の検索に利用します。
臨床試験予定に悪性腫瘍を含む場合は、悪性腫瘍/Malignancyをご選択ください。
|
|
| ゲノム情報 | Genomic information/ゲノム情報の取扱い | 必須 | ○ | 選択 | - |
定義:試験参加者のゲノム情報を入手または解析し、結果との関連性の考察などに用いるか否か。
選択肢:はい、いいえ
|
| 目的 | Narrative objectives | 必須 | ○ | テキスト | 2000 |
定義:試験を実施する目的
ノート:記述的な記載としてください。仮説やresearch questionでも結構です。
|
| 目的1 | 必須 | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Basic objectives/ 目的2 | 必須 | ○ | 選択 | - |
定義:主要アウトカム評価項目により評価する最も基本的事項
選択肢:安全性、有効性、安全性・有効性、生物学的・臨床的同等性、生物学的利用性、薬物動態、薬力学、薬物動態・薬力学、その他
選択肢の定義:
(安全性)安全性の評価を目的とした試験
(有効性)有効性の評価を目的とした試験
(安全性・有効性)安全性と有効性の評価を目的とした試験
(生物学的・臨床的同等性)既存の介入法との比較で、生物学的利用性、臨床的
有効性や安全性が同等と推定されるかどうかを検討する試験
(生物学的利用性)生体内での医薬品等の吸収の度合いを検討するために実施する試験。医薬品、ワクチン、遺伝子を用いた介入において成立する。
(薬物動態)生体内での医薬品等の吸収、分布、代謝、排泄を検討するために実施する試験。医薬品、ワクチン、遺伝子を用いた介入において成立する。
(薬力学)医薬品等の薬理作用に起因する効果や有害な作用などを検討するために実施する試験。医薬品、ワクチン、遺伝子を用いた介入において成立する。
(薬物動態・薬力学)薬物動態と薬力学試験両方の目的をもった試験
(その他)上記のいずれにも該当しない
ノート:用量反応を確認する試験においては、設定している主要アウトカム評価項目が
何かに基づき入力して下さい。有効性を示す主要アウトカム評価項目により用量
反応性を推定するのであれば、有効性、血中濃度により用量反応性を推定するの であれば、薬物動態を選んで下さい。
生物学的利用性、薬物動態、薬力学、薬物動態・薬力学を選択する場合、
医薬品、ワクチン、遺伝子を評価する試験でなければなりません。
|
|
| Basic objectives -Others | 目的2がその他の場合 | ○ | テキスト | 1000 |
定義:「目的2」が「その他」の場合の、内容
|
|
| 目的2 -その他詳細 | 目的2がその他の場合 | ○ | テキスト | 1000 | ||
| 試験の性質 | Trial characteristics_1/試験の性質1 | - | ○ | 選択 | - |
定義:仮説の検証を目的とした試験か否か
選択肢:検証的、探索的
選択肢の定義:
(検証的)すでに探索的試験などにより仮説が形成されており、その仮説を検証するために実施する試験
(探索的)検証的試験の実施の前に、仮説を形成するために実施する試験
ノート:研究グループの判断による分類で結構です。
|
| Trial characteristics_2/試験の性質2 | - | ○ | 選択 | - |
定義:試験の目的と実施状況に基づく分類
選択肢:説明的、実務的
選択肢の定義:
(説明的)介入法の作用機序などを解明する目的で、実施条件をある程度厳しく設定して実施する試験
(実務的)実施条件をゆるく設定し、日常診療に近い状況で介入法を評価するために実施する試験
ノート:研究グループの判断による分類で結構です。
|
|
| 試験のフェーズ | Developmental phase/試験のフェーズ | - | ○ | 選択 | - |
定義:医薬品あるいは治療法を開発する試験の場合、その開発段階
選択肢:第Ⅰ相、第Ⅱ相、第Ⅰ・Ⅱ相、第Ⅲ相、第Ⅱ・Ⅲ相、第Ⅳ相、該当せず
選択肢の定義:
(第Ⅰ相)開発の最も初期の段階。通常は、有効性をみることを主たる目的としない。
健康な志願者又は特定のタイプの患者で実施される。次に示す1つまたは その組合わせの観点から行われることが多い。
(第Ⅱ相)患者における介入の効果の探索を主要な目的とする段階。
(医薬品・ワクチン・遺伝子の場合、第Ⅲ相で用いる用量の決定)
(第Ⅰ・Ⅱ相)第Ⅰ相と第Ⅱ相両方の性質を持つ試験。
(第Ⅲ相)介入の利益を証明または確認することを主要な目的とする段階。
(第Ⅱ・Ⅲ相)第Ⅱ相と第Ⅲ相両方の性質を持つ試験。
(第Ⅳ相)医薬品についてのみ適用される。当該医薬品承認後に行われる市販後臨床試験。
(該当せず)医薬品や治療法の開発を目的としておらず、かつ、フェーズの概念を持たない試験である。以上のいずれにも該当しない。
ノート:医薬品や治療法の開発以外でも、該当する「相」があれば選択してください。
該当する「相」がなければ、「該当せず」を選択してください。
|
| 評価 | Primary outcome | 必須 | ○ | テキスト | 2000 |
定義:評価に用いる最も主要な指標
ノート:可能な限り、評価の時期の情報(例:投与開始から4週後
など)も含めてください。また、原則として最も主要な評価項目1つのみを記入し、他の評価項目は「副次アウトカム評価項目」としてください。また、単に「安全性」「有効性」などと記入するのではなく、どのような測定によって安全性や有効性を評価しようとするのかを記入してください。
|
| 主要アウトカム評価項目 | 必須 | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Key secondary outcomes | - | ○ | テキスト | 2000 |
定義:評価に用いる具体的で副次的な指標
ノート:可能な限り、評価の時期の情報(例:投与開始から4、8、12週後
など)も含めてください。
|
|
| 副次アウトカム評価項目 | - | ○ | テキスト | 2000 |
| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本事項 | Study
type/
試験の種類 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:介入的試験か、観察的試験か
選択肢の定義:
(介入: Interventional Study)各種の介入(医薬品、ワクチン、遺伝子、医療器具・機器、
教育・心理・行動、手技)を評価する目的で、参加者に対して介入を行う試験。侵襲の有無、程度にかかわらず、研究参加者に対して評価対象である研究目的の処置が割り付けられる場合、介入となります。
(観察: Observational Study)参加者に対して介入を行わず、特定の指標の変化などを記録する試験。指標とプロトコルで定める参加者の背景因子の関連を調べたり、ある疾患の自然な症状の推移を調べたりする試験。研究参加者以外に対しても通常診療の範囲内で実施されているような処置の評価を行う場合は、観察となります。
|
| 介入研究デザイン | (注意)以下の「介入研究デザイン」は、介入を伴う臨床試験に関する情報についてです。観察研究ではここには入力せず、「その他関連情報」の欄に自由文で詳細な情報を入力してください。 | |||||
|
Basic design/ 基本デザイン |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:最も基本的な試験デザイン
選択肢:並行群間比較、クロスオーバー試験、要因デザイン、単群、継続・拡大投与
選択肢の定義:
(並行群間比較)参加者が、2つ以上の複数の群の内の1つに割付けられる試験。
(クロスオーバー試験)すべての参加者は、同一の2つ以上の複数の介入を受けるが、介入を受ける順序が異なる。介入を受ける順序の違いで複数の群を規定し、この内1つの群に参加者を割付ける試験。この場合、介入内容の記載がウォッシュアウト期間を含めたものが必要とされますのでご注意ください。
(要因デザイン)複数の介入の、異なる組み合わせを複数用いて、2つ以上の介入を同時に評価する試験。この場合、群数は各要因数の積になるべきですのでご注意ください。
(単群)すべての参加者が同一の介入を受ける試験。
(継続・拡大投与)倫理的・救済的措置として、本試験の終了後にも引き続き介入が実施されたり、本試験に参加できなかったが試験薬の投与を希望する患者に試験薬を投与するために実施される試験。こちらを選択される場合、「その他関連情報」の欄に本試験の情報を記載してください。
|
|
| Randomization/
ランダム化 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:試験参加者に割り当てられる群が確率的要素により決定する、ランダム
割付を行うか否か 選択肢の定義:
(ランダム化)試験参加者に、確率的要素を取り入れて割り当てる群を決定
する、ランダム割付を行う。
(非ランダム化)参加者を各群にランダムに割り付けない。
ノート:「準ランダム化」試験も「ランダム化」試験としてください。
(「準ランダム化」試験の例:カルテ番号の末尾の数字等を用いて群を割り当てる) 単群で行う試験の場合は、「非ランダム化」試験としてください。 |
|
| Randomization unit/ランダム化の単位 | - | ○ | 選択 | - |
定義:どのような単位でランダム化を行い割付けるか。つまり、個々の参加者単位で
各群に割付けるか、ある特性をもった集団単位で割付けるか。 選択肢の定義:
(個別)参加者個人単位で割り付ける
(集団)ある特性をもった集団単位で割り付ける
例えば、施設をランダム化する、地域や家族ごとにランダム化する、など ノート:「ランダム化」試験の場合は、必ず記載してください。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。
|
|
| Blinding/ ブラインド化 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:試験参加者、介入実施者および測定者が、試験参加者の割付けられている群を知りえているか否か。
選択肢:オープン、オープンだが測定者がブラインド化されている、試験参加者が
ブラインド化されている単盲検、介入実施者/測定者がブラインド化されている単盲検、二重盲検
選択肢の定義:
(オープン)試験参加者、介入実施者と主要アウトカム評価項目の測定者が
割り付けられた群を知っている。この場合、介入実施者と測定者は同一でも異なった人物でもよい。
(オープンだが測定者がブラインド化されている)試験参加者と介入実施者が割付け
られた群を知っているが、主要アウトカム評価項目の測定者は、試験参加者の割付けられた群を知りえない。この場合、
介入実施者と測定者は異なる人物である。
(試験参加者がブラインド化されている単盲検)試験参加者のみ、割付けられた群を知りえない。
この場合、介入実施者と測定者は同一でも異なった人物でもよい。
(介入実施者・測定者がブラインド化されている単盲検)試験参加者は自身が割付けられた
群を知っているが、介入実施者と測定者は、試験参加者の割付けられた群を知りえない。この場合、介入実施者と測定者は同一でも異なった人物でもよい。
(二重盲検)試験参加者と主要アウトカム評価項目の測定者が、割付けられた群を知りえない。
介入実施者と主要アウトカム評価項目の測定者が異なる場合、介入実施者は知っていても、知り得なくてもどちらでもよい。
ノート:単群試験では、「オープン」を選択してください。
|
|
| Control/ コントロール |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:比較対照の種類
選択肢:プラセボ/シャム対照、実薬/標準治療対照、用量対照、ヒストリカル、無治療対照、無対照、群内
選択肢の定義:
(プラセボ/シャム対照)プラセボ投与やシャム(擬似的処置)を行った群を比較対照とする試験
(実薬/標準治療対照)既に市販されている医薬品や標準的に実施されている介入方法を実施する群を比較対照とする試験
(用量対照)互いに異なる用量を比較対照とする試験(プラセボやシャムを含んでよい)
(ヒストリカル)同時に比較群を置くのではなく、過去の試験結果を比較対照とする試験
(無治療対照)特定の試験治療をしない、あるいは日常診療の範囲内の治療しか行わない群を比較対照とする試験
(無対照)対照をおかない試験
(群内)同一群に複数の介入を順次行い、反応を比較する試験。同一患者に従来の検査法と新しい検査法を同時に実施し、検査性能を比較するような場合もこちらを選択してください。
ノート:単群試験では、「ヒストリカル」または「無対照」または「群内」を選択してください。
|
|
| Stratification/ 層別化 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:予後因子となりえる施設以外の背景因子を層別化し、1つの層の中で群の例数の分布が
均等になるように割付ける方法を採用しているか、否か。 ノート:「ランダム化」試験の場合は、可能な限り記載してください。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。 考慮する背景因子の数・種類は問いません。 |
|
| Dynamic allocation/ 動的割付 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:新しい試験参加者を割付ける際に、それまでに割付けられた群間の
背景要因のバランスを反映させて、逐次、割付けられる群が決定される方法 (動的割付)を採用しているか、否か。 ノート:「ランダム化」試験の場合は、可能な限り記載する。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。 動的割付に使用する背景因子の数・種類は問いません。 例:動的割付が「はい」である代表的手法として、最小化法が挙げられます。
|
|
| Institution consideration/
試験実施施設の考慮 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:割付において試験実施施設をどのように考慮しているか。
選択肢:動的割付において施設を調整因子としている、施設をブロックとしている、
施設を考慮していない
選択肢の定義:
(動的割付の際に施設を調整因子としている)割付の際に、試験実施施設を予後因子
として用い、各施設の中で群の分布が均等に近くなるように割り付ける方法。
(施設をブロックと見なしている)試験実施施設そのものをブロックと見なし、その
ブロックの中で群の分布が均等になるように割り付ける方法。
(施設を考慮していない)割付の際に試験実施施設を考慮していない。
ノート:「ランダム化」試験の場合は、可能な限り記載してください。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。 |
|
| Blocking/ ブロック化 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:ある人数の「ブロック」を設定し、1つの「ブロック」の中で群の例数の分布が
均等になるように割付ける方法を採用しているか、否か。 ノート:「ランダム化」試験の場合は、可能な限り記載してください。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。
例:ブロック化が「はい」である代表的手法として、置換ブロック法が挙げられます。
|
|
| Concealment/ 割付コードを知る方法 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:割付コードを作成し、管理する方法として、どのような方法を採用しているか。
介入実施者が割付け結果を予見できるか否かの指標。
選択肢:中央登録、封筒法、準ランダム化、知る必要なし
選択肢の定義:
(中央登録)介入実施者が割付に関与せず、第三者的機関において集中的に
登録を行っている。割付コードは、その第三者的機関からもたらされる。
(封筒法)割付順番に従ってあらかじめ決定された群が記入された容器(封筒)を、
介入実施者が順に開封することにより割り付ける。開封の順番は、介入実施者自身が変更しえる危険性がある。
(準ランダム化)カルテ番号や来院の順番など、準ランダム化により割付けを行って
おり、介入実施者は割付ける群を知りえる
(知る必要がない)介入実施者は、割付コードを知る必要がない。割付コードを知る
必要のない、二重盲検試験、オープン試験、単群試験の場合に選択する。
ノート:「ランダム化」試験の場合は、可能な限り記載してください。
「非ランダム化」試験の場合は、記載は不要です。 |
|
| 介入 | (注意)以下の「介入」は、介入を伴う臨床試験に関する情報についてです。観察研究では入力しないでください。 | |||||
| No. of arms/ 群数 |
必須 | ○ | 数値 | 1 |
定義:対照群も含めた群の数
|
|
| Purpose of intervention/ 介入の目的 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:介入の目的
選択肢:治療・ケア、予防・検診・検査、診断、教育・カウンセリング・トレーニング
選択肢の定義:
(治療・ケア)医療行為を伴う積極的治療(医薬品、機器、
ケア(介護・看護・リハビリテーション)、手技など)を評価する試験
(予防・検診・検査)予防を目的とした介入(検診や検査を含む)を評価する試験
(診断)診断を目的とした介入を評価する試験
(教育・カウンセリング・トレーニング)医療行為を伴わない介入(教育やトレーニングなど)を評価する試験
|
|
| Type of intervention/ 介入の種類 |
必須 | ○ | チェックボックス | - |
定義:介入の種類
選択肢:医薬品、ワクチン、遺伝子、食品、医療器具・機器、行動・習慣、手技、その他
選択肢の種類:
(医薬品)医薬品・漢方薬などの投与による介入
(ワクチン)ワクチンによる予防的介入
(遺伝子)組換えDNAを含む遺伝子導入を伴う介入
(食品)食品の摂取による介入
(医療器具・機器)医療機器・器具による介入
(行動・習慣)行動や習慣に対する介入
(手技)手術・臓器移植・細胞移植・放射線治療・鍼灸・介護・看護・リハビリテーション
(その他)化粧品等
|
|
| Interventions/ Control_1 |
必須 | ○ | テキスト | 2000 |
定義:介入群または対照群の内容の詳細。
ノート:「群数」に記載した数の内容の記載が必要です。
以下の点を参考に、可能な限り詳しく記載してください(特に、長期間にわたる投薬や機器使用の介入の場合、具体的な期間は必ず含めてください)。 ・個々の被験者に対する介入の期間 ・量(投与量や線量など) ・回数・頻度 など。 医薬品を評価する臨床試験の場合、医薬品の名称や治験薬コードも含んだ記載としてください。 また、要因デザインやクロスオーバー試験の場合、各介入の種類を説明するものではないことを注意してください。 [要因デザイン] 例えば、要因Aと要因Bの2要因の要因デザインの試験は4群で構成され、 ・介入1:要因A(-)、要因B(-) ・介入2:要因A(+)、要因B(-) ・介入3:要因A(-)、要因B(+) ・介入4:要因A(+)、要因B(+) [クロスオーバー試験] 例えば、処置Aと処置Bによるクロスオーバー試験は、2群で構成されますが、処置Aと処置Bを受ける 順序の違いで群が定義されるので、受ける処置の順序も含んだ記載としてください。 ・介入1:処置A⇒(ウォッシュアウト期間)⇒処置B ・介入2:処置B⇒(ウォッシュアウト期間)⇒処置A となるのが一般的です。 また、「介入」は患者の背景情報ではないので、「健常群」「患者群」のような被験者特性はこちらには記載しないでください。例えば、同一の検査を健常群と患者群に実施して、その結果を比較するような場合には、介入としては1種類ですので、単群試験、「介入」としては検査の具体的な内容、「コントロール」は「群内」としてご登録ください。 |
|
| 介入1 | 必須 | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_2 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入2 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_3 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入3 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_4 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入4 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_5 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入5 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_6 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入6 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_7 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入7 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_8 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入8 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_9 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入9 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Interventions/ Control_10 |
(群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | 同上 | |
| 介入10 | (群数に依存) | ○ | テキスト | 2000 | ||
| 適格性 | Age-lower limit/ 年齢(下限) |
必須 | ○ | 数値型 | 3 |
定義:参加者として適格とする年齢の下限
ノート:下限がない場合は、数値は空欄とし、年齢(下限)単位の入力欄に「適用なし」を入力してください。
|
| Age-lower limit unit/ 年齢(下限) 単位 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者として適格とする年齢の下限の単位
選択肢:歳、ヶ月、週、日、適用なし
ノート:年齢(上限)の単位と同じにしてください。
下限がない場合は、数値、年齢(下限)限界記号は空欄とし、年齢(下限)単位の 入力欄に「適用なし」を入力してください。
|
|
| Age-lower limit symbol/
年齢(下限)限界記号 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者として適格とする年齢の下限の限界記号
選択肢:以上、より上
ノート:下限がない場合は、空欄としてください。
|
|
| Age-upper limit/ 年齢(上限) |
必須 | ○ | 数値 | 3 |
定義:参加者として適格とする年齢の上限
ノート:年齢(下限)の単位と同じにしてください。
上限がない場合は、数値は空欄とし、年齢(上限)単位の入力欄に「適用なし」を 入力してください。 |
|
| Age-upper limit unit/ 年齢(上限)単位 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者として適格とする年齢の下限の単位
選択肢:歳、ヶ月、週、日、適用なし
ノート:上限がない場合は、数値、年齢(上限)限界記号は空欄とし、年齢(上限)単位の
入力欄に「適用なし」を入力してください。
|
|
| Age-upper limit symbol/
年齢(上限)限界記号 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者として適格とする年齢の上限の限界記号
選択肢:以下、未満
ノート:上限がない場合は、空欄としてください。
|
|
| Gender/性別 | 必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者として適格とする性別
選択肢:男、女、男女両方
|
|
| Key inclusion criteria | 必須 | ○ | テキスト | 2000 |
定義:参加者として適格とする主な基準
ノート:年齢、性別を含んで記載しても結構です。ただし、その際は、既に上の欄で入力して
いる内容と一致していることを確認して下さい。
臨床薬理試験などで健康な人に参加してもらう試験の場合、「健康な○○」といった 記載は、『対象疾患』ではなく、こちらに入力してください。 |
|
| 選択基準 | 必須 | ○ | テキスト | 2000 | ||
| Key exclusion criteria | 必須 | ○ | テキスト | 2000 |
定義:参加者として不適格であるとする主な基準
|
|
| 除外基準 | 必須 | ○ | テキスト | 2000 | ||
| 目標参加者数 | Target sample
size/ 目標参加者数 |
必須 | ○ | 数値 | 6 |
定義:本試験に組み入れる予定の参加者数
|
| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任研究者 | Name of lead principal investigator | 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験の科学的側面に対して責任を有する方の氏名
ノート:多施設共同研究の場合には、リーダーとなる研究者の氏名です。
同格者が2名の場合は併記してご記入ください。 記載順を日本語はあいうえお順、英語はアルファベット順にお願い致します。 |
| 責任研究者名 | 必須 | ○ | テキスト | 100 | ||
| Organization | 必須 | ○ | テキスト | 200 |
定義:本試験の科学的側面に対して責任を有する研究者の所属組織
|
|
| 所属組織 | 必須 | ○ | テキスト | 200 | ||
| Division name | 必須 | ○ | テキスト | 200 |
定義:本試験の科学的側面に対して責任を有する研究者の所属部署名
|
|
| 所属部署 | 必須 | ○ | テキスト | 200 | ||
| Address | 必須 | ○ | テキスト | 200 |
定義:本試験の科学的側面に対して責任を有する研究者の所属組織の住所
|
|
| 住所 | 必須 | ○ | テキスト | 200 | ||
| TEL/電話 | 必須 | ○ | テキスト | 50 |
定義:本試験の科学的側面に対して責任を有する研究者の所属組織の電話番号
ノート:0x-xxxx-xxxxや0xxx-xx-xxxxのように「(ゼロつきの地域番号)+(番号)」の
形式に従って入力してください。
外線番号の直後に(スペースを含まずに)、(ext.xxxxx)を追加することにより、 内線番号を示すことができます。 |
|
| 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報の責任研究者の所属組織の電子メールアドレス
|
||
| 試験問い合わせ窓口 | Name of contact person | 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる組織の担当者の方の氏名
|
| 担当者名 | 必須 | ○ | テキスト | 100 | ||
| Organization | 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる組織の名称
|
|
| 組織名 | 必須 | ○ | テキスト | 100 | ||
| Division name | 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる組織の部署名
|
|
| 部署名 | 必須 | ○ | テキスト | 100 | ||
| Address | 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる部署の住所
ノート:問い合わせを受け付けたり、情報を公開できる手段。
|
|
| 住所 | 必須 | ○ | テキスト | 100 | ||
| TEL/電話 | 必須 | ○ | テキスト | 50 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる部署の電話番号
ノート:問い合わせを受け付けたり、情報を公開できる手段。
0x-xxxx-xxxxや0xxx-xx-xxxxのように「(ゼロつきの地域番号)+(番号)」の
形式に従って入力してください。
外線番号の直後に(スペースを含まずに)、(ext.xxxxx)を追加することにより、 内線番号を示すことができます。 |
|
| Homepage URL/ 試験のホームページURL |
- | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、試験に関する情報を提供できるURL
ノート:問い合わせを受け付けたり、情報を公開できる手段。
|
|
| 必須 | ○ | テキスト | 100 |
定義:本試験情報が公開された場合、一般からの問い合わせ窓口となる電子メールアドレス
ノート:問い合わせを受け付けたり、情報を公開できる手段。
|
||
| 情報送信組織 | Name of person sending information | 必須 | × | テキスト | 100 |
定義:情報送信組織とは、試験情報を実際に登録する組織を設定するように想定しております。
たとえば、臨床試験実施責任組織、責任研究者、委託先(公益法人、企業、等)を設定できます。
本試験情報を送信した方の氏名 ノート:UMINセンターから連絡を取る可能性がありますので、確実に連絡をとれるように
記入をお願いします。
|
| 送信者名 | 必須 | × | テキスト | 100 | ||
| Organization | 必須 | × | テキスト | 200 |
定義:本試験情報を送信した方の所属組織名
|
|
| 情報送信組織 | 必須 | × | テキスト | 200 | ||
| Division name | 必須 | × | テキスト | 100 |
定義:本試験情報を送信した方の所属部署
|
|
| 所属部署 | 必須 | × | テキスト | 100 | ||
| Address | 必須 | × | テキスト | 200 |
定義:本試験情報を送信した方の所属組織の住所
|
|
| 住所 | 必須 | × | テキスト | 200 | ||
| TEL/電話 | 必須 | × | テキスト | 50 |
定義:本試験情報を送信した方の所属組織の電話番号
ノート:0x-xxxx-xxxxや0xxx-xx-xxxxのように「(ゼロつきの地域番号)+(番号)」の
形式に従って入力してください。
外線番号の直後に(スペースを含まずに)、(ext.xxxxx)を追加することにより、 内線番号を示すことができます。 |
|
| 必須 | × | テキスト | 100 |
定義:本試験情報を送信した方の電子メールアドレス
|
||
| 試験実施責任組織 | Name of primary sponsor | 必須 | ○ | テキスト | 200 |
定義:試験の計画、解析と結果公表、研究費調達を含めた実施のための 運営管理に対して責任を持つ組織
ノート:研究費提供の概念とは別です。
どの臨床試験においても「なし」はあり得ません。 例:
- 医薬品や医療機器の臨床開発段階の試験⇒治験依頼者である企業名 - その他の臨床試験(医師主導治験、科研費を受けて実施する臨床試験、 科研費以外で各種団体から助成金を受けて実施する臨床試験 自主的臨床試験など) ⇒試験実施計画書の作成や、実施のための運営管理などを中心的に 行っている研究グループ(特定の病院の医局でも可)など |
| 実施責任組織 | 必須 | ○ | テキスト | 200 | ||
| 研究費提供組織 | Funding source | 必須 | ○ | テキスト | 200 |
定義:研究費を支給している、最も主要な組織(1組織)。
ノート:支給の形態は契約、助成、寄付などを問いません。
また、試験の説明会等の会場費負担・交通費支給、症例登録施設への研究協力費支払や 金銭に限らず現物提供 等を行っている組織も相当します。 原則として、研究費の提供の割合が最も高い組織が相当します。 複数から提供を受けている場合、「その他の研究費提供組織」に提供割合が2位以下の 組織を記載してください。 どこからも助成をうけないで実施する臨床試験では、「なし」「None」としてください。 例:
- 医薬品や医療機器の臨床開発段階の治験⇒治験依頼者である企業名 - 科研費を受けて実施する臨床試験⇒科研費を支給している省庁 (研究班やプロジェクトの名称の入力は不要です) - 科研費以外で各種団体から助成金や寄付を受けて実施する臨床試験 ⇒助成、寄付している団体 |
| 研究費提供組織 | 必須 | ○ | テキスト | 200 | ||
| Category of Org./組織の区分 | 必須 | ○ | 選択 | - |
定義:研究費提供組織の区分。
選択肢:厚生労働省、文部科学省、農林水産省、財団等、営利企業、自己調達
ノート:文部科学省には学術振興会を含みます。
「財団等」には、NPO、一般社団法人も含まれます。 どこからも研究費提供を受けていない場合、自己調達としてください。 |
|
| Nation of funding | - | ○ | テキスト | 100 |
定義:研究費を提供している組織の存在している国
|
|
| 研究費拠出国 | - | ○ | テキスト | 100 | ||
| その他の関連組織 | Co-sponsor | - | ○ | テキスト | 4000 |
定義:試験実施責任組織と研究費提供組織以外の組織で、共同研究などで試験の実施に
関係している組織。
ノート:一般的には、試験実施施設であるというだけでは、共同実施組織に相当しません。
なければ記載は不要です。複数ある場合は、箇条書きにしてください。
例:
- 医師主導治験において医薬品などの提供を受けている場合、提供元の企業 |
| 共同実施組織 | - | ○ | テキスト | 4000 | ||
| Name of secondary funder | - | ○ | テキスト | 200 |
定義:試験実施責任組織と研究費提供組織以外の組織で、研究費、被験薬などの
試験関連資材等を提供している組織。複数ある場合は、箇条書きにしてください。
ノート:なければ記載は不要です。
例:
- 医師主導治験において医薬品などの提供を受けている場合、提供元の企業 |
|
| その他の研究費提供組織 | - | ○ | テキスト | 200 | ||
| IRB等連絡先 | Research ethics review/
倫理委員会による審査・承認 |
必須 | × | 選択 | - |
定義:臨床試験の実施について倫理委員会からの承認の有無を明記する
ノート:倫理委員会を複数保有している臨床試験は全ての倫理委員会から承認を得てから
(はい/YES)を選択ください。
|
| Post marketing survey by drug manufacture etc.,
specified by Japanese law./ 日本の法規に定める医薬品製造業者等による医薬品の市販後調査への該当 |
必須 | × | 選択 | - |
ノート:
◆IRBの「組織名」「住所」「電話」「Email」が必須となる選択肢
・該当なし ・市販後臨床試験 ◆IRBの「組織名」「住所」「電話」「Email」が任意となる選択肢
・市販後使用成績調査 ・市販後特定使用成績調査 |
|
| Organization1/ 組織名1 |
必須 | × | テキスト | 200 |
定義:公開用の、主要なIRBの設置されている組織名。
ノート:IRBのうち、主要な1組織について、住所、電話番号、電子メールアドレス等を記載してください。
連絡が取るのに十分な情報が記載されていれば、必ずしも全ての情報を記載する必要はありません。
記載できない場合は N/A などとしてください。
|
|
| Address1/住所1 | 必須 | × | テキスト | 200 |
定義:試験進捗などをUMINセンターから問い合わせる際の、主要なIRBの設置されて
いる組織の住所
|
|
| TEL1/電話1 | 必須 | × | テキスト | 50 |
定義:試験進捗などをUMINセンターから問い合わせる際の、主要なIRBの電話
ノート:0x-xxxx-xxxxや0xxx-xx-xxxxのように「(ゼロつきの地域番号)+(番号)」の
形式に従って入力してください。
外線番号の直後に(スペースを含まずに)、(ext.xxxxx)を追加することにより、 内線番号を示すことができます。 |
|
| E-mail1 | 必須 | × | テキスト | 100 |
定義:試験進捗などをUMINセンターから問い合わせる際の、主要なIRBに連絡をとることができる電子メールアドレス
ノート:試験進捗などの問い合わせは、情報送信者にも「cc」として連絡が入るようにするので、
可能な限り IRBに直接連絡がとれるアドレス(IRBとしての代表アドレスや、
委員の方のアドレス)を記載してください。
|
|
| Organization2/ 組織名2 |
- | × | テキスト | 200 | 同上 | |
| Address2/住所2 | - | × | テキスト | 200 | 同上 | |
| TEL2/電話2 | - | × | テキスト | 50 | 同上 | |
| E-mail2 | - | × | テキスト | 100 | 同上 | |
| Organization3/ 組織名3 |
- | × | テキスト | 200 | 同上 | |
| Address3/住所3 | - | × | テキスト | 200 | 同上 | |
| TEL3/電話3 | - | × | テキスト | 50 | 同上 | |
| E-mail3 | - | × | テキスト | 100 | 同上 | |
| 審査・承認 | Research ethics
review/
倫理委員会による審査・承認 |
入力不要 | ○ | - | - |
定義:倫理委員会により、臨床試験が審査され承認されたものであるか否か。
ノート:「IRB連絡先」に入力されたデータにより自動判別します。少なくとも1箇所の組織について有効なデータが入力されていた場合、「はい/Yes」が表示されます。
|
| 試験ID | Secondary Study IDs/
他の機関から発行された試験ID |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:他の登録機関に試験を登録し、IDの発行を受けているか否か。
選択肢:はい、いいえ
|
| Secondary Study
ID_1/ 試験ID1 |
(ID「あり」の場合必須) | ○ | テキスト | 50 |
定義:他の登録機関からIDを発行されている場合のID。
ノート:「国際的機関から発行されたIDの有無」が「無」の場合は、記入不要です。
|
|
| Org. issuing secondary Study ID_1 | (ID「あり」の場合必須) | ○ | テキスト | 200 |
定義:他の機関からIDを発行されている場合のID発行機関。
ノート:「国際的機関から発行されたIDの有無」が「無」の場合は、記入不要です。
|
|
| ID発行機関1 | (ID「あり」の場合必須) | ○ | テキスト | 200 | ||
| Secondary Study
ID_2/ 試験ID2 |
- | ○ | テキスト | 50 |
定義:他の登録機関からIDを発行されている場合のID。
ノート:「他の機関から発行されたIDの有無」が「無」の場合は、記入不要です。
|
|
| Org. issuing secondary Study ID_2 | - | ○ | テキスト | 200 |
定義:他の機関からIDを発行されている場合のID発行機関。
ノート:「他の機関から発行されたIDの有無」が「無」の場合は、記入不要です。
|
|
| ID発行機関2 | - | ○ | テキスト | 200 | ||
| Unique trial
number/ 試験識別番号 |
- | ○ | テキスト | 50 |
(暫定)定義:WHOから臨床試験に対して発行される国際的に一意なID番号。
|
|
| IND to MHLW/治験届初回届 | - | ○ | テキスト | 50 |
定義:日本で実施しており、日本の厚生労働省に「治験届」を提出している場合の、初回届出年月日と届出回数
|
|
| 試験実施施設 | Institutions/ 試験実施施設名称 |
- | ○ | テキスト | 2000 |
定義:本試験を実施する予定施設名称と所在都道府県
例:○○大学病院(東京都)、△△病院(愛知県)、××医院(大阪府)
|
| 本登録希望日 | Date of disclosure of the study
information/ 試験情報の本登録希望日(=公開日) |
必須 | (注)× ↓ ○ |
日付 | - |
定義:登録した臨床試験の存在および情報を一般に公開する日付
ノート:試験の結果を含めた"すべての情報"を公開する希望日ではありません。
UMIN-CTRでは、まず試験の存在を公開し、この時点の情報をベースに、情報の変更、試験進捗の推移や結果を反映していくことを想定しています。 これから実施する試験の場合、登録作業の当日や、参加者の登録・組み入れ開始 予定日、すでに開始したり終了したりしている試験の場合、登録作業の当日を 設定するのが一般的です。 必ず、登録作業の当日かそれ以降の日付である必要があります。 また、本登録希望日(=公開日)に達した日付以降(試験が公開された場合)、本登録希望日は変更できません。 (注):試験の公開前は×(非公開)、試験の公開後は○(公開) |
| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験進捗状況 | Recruitment
status/ 試験進捗状況 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:参加者登録や試験の進行状況
選択肢:開始前、一般募集中、限定募集中、参加者募集中断、参加者募集終了-試験継続中、主たる結果の公表済み、試験中止、試験終了
ノート:一般募集中は(参加医療機関受診により、基準を満たせば被験者となれる)
限定募集中は(参加医療機関受診中の患者が、基準を満たす場合に被験者になれる)
※旧選択肢の[参加者募集中/Recruiting]を選択されていた場合には、
再選択が必要。再選択されるまでは、[参加者募集中]が表示される。 試験終了について、
1.プロトコールに試験終了時点をいつにするか記載があればその時点とする。
2.プロトコールに試験終了時点について記載が無ければ、UMIN
CTRとしては試験終了時点を下記と規定する。
2-1.単施設臨床試験の場合データ固定後、IRBに試験終了報告がなされた日
2-2.多施設臨床試験の場合試験中央事務局がデータ固定後に全施設でIRBに試験終了報告がなされたことを確認後
試験終了宣言した日(各施設の試験終了日は異なるため)
|
| Date of protocol fixation/ プロトコル確定日 |
必須 | ○ | 日付 | - |
定義:プロトコルが確定した日付。
|
|
| Anticipated trial start date/
登録・組み入れ開始(予定)日 |
必須 | ○ | 日付 | - |
定義:最初の参加者の登録・組み入れ開始予定日。最初の参加者が登録
された後は、実際に最初の組み入れが行われた日付。
ノート:試験の登録時は、予定の日付を記載し、実際に登録が行われた後、必要に応じて
データを更新してください。
|
|
| Last follow-up date/ フォロー終了(予定)日 |
必須 | ○ | 日付 | - |
定義:最後の参加者の最終観察予定日。最後の参加者の観察が終了した後は、実際に観察が終了した日付。
ノート:試験の登録時は、予定の日付を記載し、実際に観察が終了した後、必要に応じて
データを更新してください。
|
|
| Date of closure to data
entry/ 入力終了(予定)日 |
- | ○ | 日付 | - |
定義:試験データの入力終了予定日。データ入力が終了した後は、実際に最後の入力が実施された日付。
ノート:試験の登録時は空欄でもかまいませんが、試験の進捗状況が「試験中止」「試験終了」
になった段階では記載が必要です。また、実際に入力が終了した後、必要に応じてデータを更新してください。
|
|
| Date trial data considered
complete/ 試験終了データ固定(予定)日 |
- | ○ | 日付 | - |
定義:試験データの固定予定日。データが確定した後は、実際にデータが確定した日付。
ノート:試験の登録時は空欄でもかまいませんが、試験の進捗状況が「試験中止」「試験終了」
になった段階では記載が必要です。また、実際にデータ固定した後、必要に応じてデータを更新してください。
|
|
| Date analysis concluded/
解析終了(予定)日 |
- | ○ | 日付 | - |
定義:解析が終了し、結論を得る予定日。解析が終了した後は、実際に解析が終了した日付。
ノート:試験の登録時は空欄でもかまいませんが、試験の進捗状況が「試験中止」「試験終了」
になった段階では記載が必要です。また、実際に解析が終了した後、必要に応じて データを更新してください。
|
|
| 関連情報 | URL releasing protocol/
プロトコル掲載URL |
- | ○ | テキスト | 100 |
定義:プロトコルが一般に公開され、閲覧できるURL。
ノート:公開された試験結果を解釈するために、原則としてプロトコルは、試験結果の公開時までには一般公開されるべきです。もし一般公開できない場合は、その旨を記載してください。また、商業的広告を主な目的とするサイトは入力しないで下さい。
|
| Publication of results/ 試験結果の公開状況 |
必須 | ○ | 選択 | - |
定義:本試験の結果の公開状況
選択肢:未公表、公表されている
ノート:結果の公開先の種類(論文、学会発表、HPへの掲載 など)は問いません。
|
|
| 結果等 | URL releasing results/ 結果掲載URL |
- | ○ | テキスト | 100 |
定義:本サイトへの試験結果記載とは別に、結果が一般に公開され、閲覧できるURL。
ノート:結果の公開先の種類(論文、学会発表、HPへの掲載 など)は問いません。
試験結果を本サイトへ記載することは必須ですが、本サイトへの記載内容以外の情報を一般公開していない場合は、その旨を記載してください。
|
| Results | - | ○ | テキスト | 512 |
定義:主要な結果の記述
ノート:フォロー終了(予定)日から12ヶ月目以降に更新を行う場合、この項目の記載が必須となります。
こちらの欄には結果ページ全体での記載内容の要約を記入してください。 なお、こちらの欄に最初に何らかの記載があった日付が「主な結果入力日」として自動的に記録され、後から修正はできません。 こちらの欄には「未定」や「今後記載予定」といった一時的な記載を行わないよう、十分にご注意ください。 |
|
| 主な結果 | - | ○ | テキスト | 512 | ||
| Results Delayed Results Delay Reason |
- | ○ | テキスト | 2000 |
定義:
ノート:フォロー終了(予定)日から12ヶ月を経過しているが、試験結果を掲載できる状況でない場合、こちらにチェックをして理由を記載してください。これにより、「主な結果」欄が空欄であっても更新を進めることが可能になりますが、本来は速やかに試験結果を公開することが求められますので、遅延理由は具体的に記載してください。
|
|
| 結果掲載遅延 結果掲載遅延理由 |
- | ○ | チェックボックス、テキスト | 2000 | ||
| Date of the first journal publication of results/ 最初の試験結果の出版日 |
- | ○ | 選択 | - |
定義:試験結果が学術誌に最初に出版された日付
ノート:未掲載の場合は日付を選択しないままとしておいてください。
|
|
| Baseline Characteristics | - | ○ | テキスト | - |
定義:被験者全体、および群ごとの参加者背景。
ノート:年齢、性別など被験者背景の分布を全体および群ごとに記載してください。
記載例はEQUATOR network, CONSORT声明、ClinicalTrials.gov などを参考にしてください。
|
|
| 参加者背景 | - | ○ | テキスト | - | ||
| Participant flow | - | ○ | テキスト | - |
定義:ランダム割付けされた人数、ランダム化後の除外人数、各群の追跡人数と追跡不能人数、各群で意図された治療を受けた人数、
主要アウトカムの解析に用いられた人数などを記載。
ノート:いわゆる参加者フローチャートを記載するために必要な情報を含めてください。
登録システムによってはPDF形式の書類をアップロードすることもある項目ですが、UMIN-CTRではテキストでの記載をお願いしています。
CONSORT声明での「参加者の流れ」に対応しています。
|
|
| 参加者の流れ | - | ○ | テキスト | - | ||
| Adverse events | - | ○ | テキスト | - |
定義:研究期間中もしくは研究終了後一定期間内に観測された、被験者に起こった望ましくない変化を記載。介入との関係の有無は問わない。
|
|
| 有害事象 | - | ○ | テキスト | - | ||
| Outcome measures | - | ○ | テキスト | - |
定義:主要評価項目および副次評価項目のすべてについて、群ごとに、精度(例えば95%信頼区間)とともに値を記載。
適切な統計解析の結果があればそれも記載。
ノート:表形式での記載が望ましいですが、本システムの制約により入力欄にはテキストしか記載できないので、文章で記載していただくか、
Markdownの表形式などを用いてご記入ください。なお、HTMLタグは利用できませんのでご注意ください。
|
|
| 評価項目 | - | ○ | テキスト | - | ||
| Plan to share IPD | - | ○ | テキスト | 255 |
定義:匿名化された個別症例データの共有を行う計画の有無を記載。
ノート:「共有」は必ずしも一般公開を意味しません。申し込みに対して審査を行い限定的に提供する場合でも「共有計画あり」となります。
こちらの欄には共有計画があるか、ないか、未定であるかを簡潔に記載してください。
|
|
| 個別症例データ共有計画 | - | ○ | テキスト | 255 | ||
| IPD sharing Plan description | - | ○ | テキスト | 2000 |
定義:匿名化された個別症例データの共有計画の詳細を記載。
ノート:共有計画がない場合はこちらにもその旨を記載してください。
共有計画がある場合には、収集したデータのうちどの部分を、いつ、どのような方法で、誰に対して、どのような解析のために共有する計画であるのかを記載してください。
記載例:匿名化された個別症例データは、試験結果の出版の1年後から、2年間の間提供する。
データおよび関連文書はウェブサイトから登録を行った者に対して無償で提供される。利用目的は問わず、審査も行わなれない。契約締結は不要である。
|
|
| 個別症例データ共有計画の詳細 | - | ○ | テキスト | 2000 | ||
| その他 | Other related information | - | ○ | テキスト | 2000 |
定義:関連する情報を自由に記載できる欄。
ノート:入力欄が設定されておらず、入力できていないが、重要な情報がある場合には、入力をお願いします。
「継続・拡大投与」試験の場合は、こちらに本試験の情報(UMIN試験IDなど)をご記載ください。
観察研究の場合は、この欄に研究デザイン(コホート研究、症例対照研究など)、
対象者の募集方法(XX年XX月-XX月に当施設を受診した患者で選択基準に合致した全員、など)、
測定する項目等を可能な範囲でご記載ください。とくに、対象者の募集方法、募集を行った期間については観察研究では重要になりますので、できるだけご記載ください。
|
| その他関連情報 | - | テキスト | 2000 |
| 分類 | フィールド名 | 必須 | 公開 | フィールド型 | サイズ(Byte) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データ管理用情報 | Receipt No./ 受付番号 |
入力不要(自動発番) | × | - | - |
定義:試験実施地域、試験簡略名、試験名を送信した後に割り当てられる番号。
自動的に発行される。 |
| Secondary ID (Unique ID issued by UMIN)/ UMIN試験ID |
入力不要(自動発番) | ○ | - | - |
定義:UMINから発行する試験に対する正式なID。自動的に発行される。
|
|
| Status/状態 | 入力不要 | × | - | - |
定義:試験の登録の状態(ステータス)を示す。入力中または登録済。
|
|
| Applicant for provisional
registration/ 初回申請者 |
入力不要 | × | - | - |
定義:当該の試験情報を最初に送信した方のUMIN ID(氏名)
|
|
| Date of provosional
registration/ 初回申請日 |
入力不要 | × | - | - |
定義:最初に臨床試験情報を登録申請した日付
|
|
| Date of
registration/ 仮登録日 |
入力不要 | ○ | - | - |
定義:定義:UMIN試験IDが発行された日付。
|
|
| Applicant for registration/ 初回申請者 |
入力不要 | × | - | - |
定義:当該の試験情報を登録処理(最終確認作業後に送信)した方のUMIN ID(氏名)
|
|
| Person last updated/ 更新者 |
入力不要 | × | - | - |
定義:既に受付番号またはUMIN試験IDが発行された試験のデータ内容を更新した者の氏名。
|
|
| Date of last update/ 最終情報更新日 |
入力不要 | ○ | - | - |
定義:既に受付番号またはUMIN試験IDが発行された試験のデータ内容を更新した日付
|
|
| UMIN ID of person who is permitted to ammend the
information/ 更新許可者UMIN ID |
- | × | - | - |
定義:受付番号またはUMIN試験IDが発行された試験のデータ内容を更新することを許可する者のUMIN
ID
ノート:最高3名まで設定できます。
|
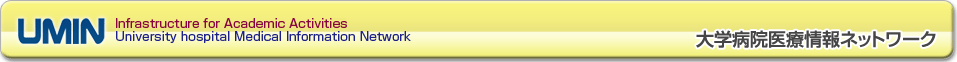
Copyright c 2013- University hospital Medical Information Network (UMIN) Center