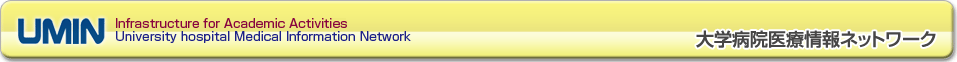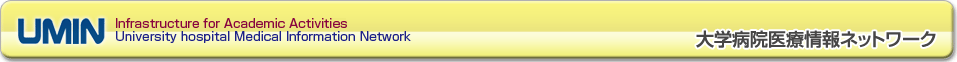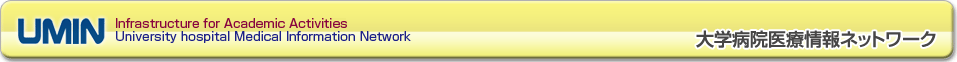3.[解説] 癌化学療法の現状と副作用対策−−抗癌剤の適正な使用のために−−
直接細胞毒性により抗癌作用を示す抗癌剤では、すべての細胞に程度の差はあれ毒
性を示す。したがって、その適応の選択や使用の際は、他の医薬品に比べ一層の注意
が必要となる。
現在、抗癌剤の有効性は承認段階では腫瘍の縮小により評価されており、例えばそ
の大きさがある期間に半分以下に縮小することをもって有効としている。現在用いら
れている抗癌剤の単剤使用における奏効率は、固形癌の場合ではおおむね20〜30
%である。
安全性については、抗癌剤の至適用量と毒性に対する最大耐用量(MTD)が極め
て近いことから、ほとんどすべての症例で骨髄抑制や消化器官障害などが問題となる。
これらの副作用は重篤な場合には死亡に至ることもあるため、定期的な臨床検査や経
過観察が極めて重要である。
抗癌剤を適正に使用するためには、患者の疾病の状態やPS(performance status
)、化学療法の特色や限界、副作用の程度、患者のQOLなどを十分に勘案し、慎重
な決定がなされる必要がある。
1.序
抗癌剤は、直接細胞毒性により抗癌作用を示す医薬品と、BRM(biological res-
ponse modifier)作用により間接的に抗癌作用を示す医薬品及びその他の医薬品の3種
類に大きく分けることができる。ここでは直接細胞毒性により抗癌作用を示す医薬品
を取り上げる。これに分類される医薬品は、基本的に細胞に対する毒性により薬効を
示す医薬品であり、活発な細胞分裂を行っている細胞すべてに程度の差はあれ毒性を
示す。このため、適応の選択や使用にあたっては、解熱鎮痛薬など他の医薬品の使用
に比べ一層高度な注意や綿密な観察が必要である。
2.抗癌剤の薬効評価
癌は予後不良の疾患であり、しかも一部の癌種を除いては化学療法の力量はいまだ
十分満足できるものではない。一方で癌は年間死亡者が20万人を超えるなど社会的
にも重大な疾患となっていることから、より優れた抗癌剤の速やかな臨床使用が望ま
れている。これらの背景から抗癌剤の承認審査は他の医薬品と異なり、いわゆる臨床
第2相試験までのデータで行われ、検証レベルの試験は市販後において行われる状況
となっている。このため、抗癌剤の使用を考慮する場合(特に新医薬品)は、次の事
項に配慮する必要がある。
1)有効性の評価は、腫瘍の縮小効果によりなされたものであり、化学療法による
延命効果は確認されていないことが多い。
2)有効性の評価は単独で行われていることが多いが、一方医療の場では単剤によ
る治療はまれで、他の抗癌剤等との併用投与がほとんどである。それら併用療法
の有効性や安全性の評価は市販後の調査を待って得られるものである。
3.抗癌剤の安全性
抗癌剤の至適用量は、ヒトのその抗癌剤の毒性に対するMTDと極めて近い場合が
ほとんどである。したがって、何らかの副作用が発現しても、それが生命を直接危険
にさらす水準とならないかぎり、治療が継続されることが多い。つまり何らかの副作
用が発現することは、薬効を期待する以上やむを得ない側面があり、最も影響を及ぼ
す副作用が、用量規制因子(DLF)として示される。DLFは細胞分裂を行ってい
る器官に対する毒性からあらわれることが多く、骨髄抑制や消化器官障害などがあり、
重篤な場合には死亡に至ることもある。特に骨髄抑制は多くの抗癌剤のDLFとなる
とともに、自覚症状が認められない場合もあるため、投与中の定期的な臨床検査の実
施や慎重な経過観察による抗癌剤の投与継続の可否についての判断が極めて重要であ
る。
このように、抗癌剤の投与による副作用発現は薬効と表裏を成しており、投与にあ
たっては慎重な配慮が必要である。
4.抗癌剤の適用
造血器腫瘍や小児癌では化学療法による治療成績がよく、完治例も少なくない。し
かし、固形癌の場合は、抗癌剤の腫瘍縮小効果から評価した奏効率は、癌種によって
異なるが、単剤ではおおむね20〜30%である。また、術後の補助化学療法は、有
効であるとする評価が確認されていない場合が多い。多くの固形癌に対する化学療法
の奏効率及び延命効果の改善や、標準的化学療法の確立は現在でも大きな課題となっ
ている。なお、2.に述べた背景により、抗癌剤は製造販売が承認された後も、臨床
第3相試験による検証的試験研究が引き続き行われることが多い。
癌に対する治療は、化学療法のほか、外科的なもの、放射線によるものなどがある。
これらの中で固形癌については外科的な治療が適応である場合、その治療成績の現状
から、奏効率の低い化学療法を選択することは倫理的にも問題が残る。抗癌剤の適応
を考える場合には、患者の疾病の状況やPSは言うまでもなく、化学療法の特色や限
界、副作用の状況や程度、患者のQOLなどを十分に勘案し、慎重な決定がなされる
必要がある。
(本稿は、国立がんセンター研究所 西條長宏先生の御意見、御指導を基に薬務局安
全課において作成したものです。)